【薬価収載・承認】アイザベイ®(アバシンカプタド ペゴルナトリウム)を徹底解説|萎縮型AMD(地図状萎縮)に挑む“補体C5阻害”の新潮流
執筆:バイオベンチャーMRかいり|カテゴリ:眼科/希少高ニーズ・新薬解説|公開日:2025年11月5日
結論:萎縮型加齢黄斑変性(GA)にはこれまで決定的な薬物療法が存在しませんでした。アイザベイは、網膜の萎縮進行そのものを“遅らせる”ことを目的とする補体C5阻害薬。2025年11月12日に薬価収載(承認:2025年9月19日)され、国内実装フェーズへ。眼科診療の「未充足」に切り込む注目薬です。
👔 外資バイオ・眼科領域の非公開求人をチェック
上市直前〜立ち上げ期のMR/MA/MAA求人はスピード勝負。専門エージェントで網羅的に比較を。
※登録・相談は無料/最短即日で求人紹介
1. 製品概要(国内)
- 一般名:アバシンカプタド ペゴルナトリウム(abacincaptad pegol sodium)
- 販売名:アイザベイ® 硝子体内注射液 20mg/mL
- 承認日:2025年9月19日(条件付き承認/再審査期間8年)
- 薬価収載日:2025年11月12日
- 効能・効果(国内想定表現):萎縮型加齢黄斑変性における地図状萎縮(GA)進行の抑制
- 剤形・規格:2mg/0.1mL(1バイアル)
- 薬価:2mg/0.1mL 1瓶 142,522円(原価計算方式/有用性加算II付与・加算係数0)
2. 用法・用量(ポイント)
初回〜12か月:月1回 硝子体内投与(2mg)
13か月以降:2か月に1回 硝子体内投与
※実臨床での最終判断は最新の添付文書・適正使用ガイドに従ってください。
3. 作用機序:補体C5阻害で“萎縮拡大”のスピードを緩める
加齢黄斑変性のうち萎縮型(GA)では、補体経路の過剰活性化が網膜色素上皮(RPE)や視細胞の変性・細胞死を加速します。アイザベイはC5を標的とすることで、炎症性カスケードと膜侵襲複合体形成の下流を抑制し、地図状萎縮の拡大速度を遅らせることを目指します。
4. 有効性エビデンス(要約)
- 国際P3試験では、偽薬群に比べGA病変拡大の抑制を示す結果が報告。投与スケジュール(毎月→隔月)下でも有意差を確認。
- 臨床的ベネフィットは「進行の遅延」であり、既存病変の回復ではない点を患者教育で強調。
5. 安全性・モニタリング
| 主な留意点 | ポイント |
|---|---|
| 眼内炎・眼圧上昇 | 無菌操作・注射手技の標準化。術後の感染徴候・圧管理。 |
| 滲出型AMDの新規発症・増悪 | 補体阻害薬では脈絡膜新生血管の発現監視が重要。OCT/OCTAでの定期評価。 |
| 患者説明 | 治療目標は「萎縮の進行を遅らせる」こと。視力改善薬ではない点を明確化。 |
6. 経済性の目安(薬価ベース概算)
- 1年目:月1回×12回 → 約1,710,000円
- 2年目:隔月×6回 → 約855,000円
※薬剤費のみの概算(薬価×回数)。実際は手技料・検査料・施設係数等で上下します。
7. 対象患者の選定と導入フロー(実装のコツ)
- 患者抽出:OCTでGAを伴う萎縮型AMDを同定。過去の滲出歴・併用治療歴を棚卸し。
- 治療ゴール設定:進行速度と視機能のトレードオフを説明。治療継続性を事前確認。
- モニタリング:OCT/OCTAで萎縮輪郭とCNV兆候を定期評価。炎症・眼圧・感染徴候を標準プロトコルで。
8. 競合理解(簡易)
- SYFOVRE®(ペグセタコプラン):C3阻害薬(海外)。作用点が上流で、炎症抑制の広さと安全性プロファイルのバランスが争点。
- アイザベイ:C5阻害。萎縮進行抑制のエビデンスをベースに、月1→隔月へ移行する運用設計が特徴。
9. MR・薬局・病院事務の実務チェックリスト
- 適正使用ガイドと患者資材(説明文書・同意書)の整備
- 注射室動線(無菌操作/術後観察スペース)の標準化
- OCT/OCTAの評価タイムライン(導入前→月次→隔月)
- 請求コード・出来高/DPC運用の確認、院内見積りテンプレ整備
💼 アイザベイ時代の眼科MRキャリアを設計する
希少高ニーズ×新薬立ち上げの“いま”を取りこぼさないために。
10. まとめ
アイザベイは、GAという“見えにくい未充足”へ初めて本格的に介入しうる選択肢。補体C5阻害×月1→隔月という実装しやすい設計と、薬価収載により診療現場での選択肢が現実に。患者説明・モニタリング設計・経済性の三位一体で、眼科医療の新しい標準づくりが始まります。
※本稿は公開情報に基づく総説であり、最終的な適正使用は添付文書・医療機関の運用に従ってください。

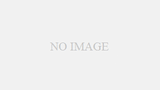
コメント