国内MR数、11年連続減少時代をどう生き残るか?
かつては「高収入」「安定職」の象徴でもあったMR(医薬情報担当者)という仕事。
しかし、国内MR数は11年連続で減少し、ピーク時の6万人から現在では4万3646人(2024年時点)にまで減少しました。
本記事では、なぜMRはここまで減少したのか?その背景と今後の展望、そしてこの業界で「生き残るMR」になるために何をすべきかを具体的に解説します。
📉 なぜMRは減少を続けているのか?
1. 早期退職を伴う組織改革の加速
武田薬品、アステラス、第一三共をはじめとする大手製薬企業では、早期退職募集による組織スリム化が進んでいます。MR職はその対象になりやすく、社内外の人員整理が繰り返されています。
2. プライマリーケアからスペシャリティ領域への構造転換
かつて多くのMRが活躍したプライマリー領域(高血圧、糖尿病など)は、ジェネリック普及や薬価低下により利益が出づらくなっています。一方、オンコロジーや希少疾患など専門領域へシフトが進み、それに伴い「高スキル・少人数」体制が主流となっています。
3. M&A・合併による人員重複の整理
2025年の塩野義製薬による鳥居薬品の買収は、営業組織の統合を目的の一つとしており、重複人材の整理が避けられません。今後も業界再編は続くと見られ、MRのポジションはますます希少になります。
🔍 減少の背景にある「経済・構造的要因」
1. 国内製薬企業の開発力と財務構造
多くの国内企業では、グローバル展開が進まず、開発の遅れと売上の頭打ちが課題となっています。新薬が出せなければ営業活動の意義も失われ、MRの必要性も減少します。
2. 外資系企業の採算主義と拠点撤退
ファイザーやJ&J、アムジェンなど外資系企業では、採算性が合わない地域や疾患領域からの撤退が進み、「日本市場の優先度低下」によりMRポジションがクローズされる例も増えています。
3. デジタル化と医師接触機会の激減
コロナ禍を経て、医師との面談は減り、Web講演会やオンライン資材提供が主流になりました。これにより、訪問主体だった従来型MRの存在意義が問われるようになっています。
💡 これから評価される「生き残るMR」の条件とは?
1. 売上以外の「社内評価」を意識する
売上だけで評価される時代は終わりました。マーケティング部門やMSLとの連携、製品戦略への貢献など、社内での横断的価値が評価基準に加わっています。
2. 専門領域へのスキルシフト
オンコロジーや希少疾患など、高度な知識と医師対応力が求められる分野への転職は、年齢や勤務地に依存しない価値を生むため、長期的に有利です。
3. 顧客とのパイプライン構築力
単なる製品紹介ではなく、医師の臨床課題を理解し、ソリューションを提供できるMRは圧倒的に重宝されます。信頼関係の構築力が差を生む時代です。
4. 異動・副業で「職能ポートフォリオ」を拡げる
社内異動でMAやマーケティングを経験したり、副業で医療系ライティングやセミナー講師を行うことで、「営業しかできない人材」から脱却することが可能です。
🏃 MRが今、動くべきこととは?
- オンコロジー・希少疾患領域への転職を視野に、知識と資格をアップデートする
- 医療業界に強い転職エージェントと面談し、市場価値を客観視する
- 今後10年を見据えて、社内キャリア戦略を再構築する
- 副業や兼業を通じて、新たな収入源とスキルを構築する
🔚 まとめ:MRという職種が「減る中で、選ばれるMR」になる時代へ
MR職は縮小を続けていますが、それは「全員が不要になる」という意味ではありません。価値を示せるMRは今後も必要とされます。
時代の変化に適応し、自らのキャリアを戦略的に構築できるMRこそが、生き残るだけでなく、業界でリーダーとなる存在になれるでしょう。
今こそ、動き出す時です。
📣 キャリアアップ・転職を考えるMRの皆様へ
オンコロジー・希少疾患領域への転職を含めたキャリア相談は、以下のエージェントで専門的な支援が受けられます。
現職に不安を感じている方も、「今より高く評価されたい」と思っている方も、一度相談してみる価値は十分にあります。
未来は、今の一歩から始まります。


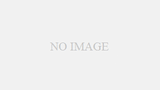
コメント